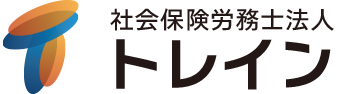2025年以降の人事労務関連動向の展望その1
2025.1今回は、2025年に向けて労基法の改正動向をはじめ人事労務まわりの今後について展望します。
1.今後の労基法改正の展望は?
厚労省の労働基準関係法制研究会は、労基法の見直しに向け、次の4点を盛り込んだ報告書のたたき台を発表しました。今年度中に最終報告書を取りまとめ、労働政策審議会で法改正議論が進められます。
- 労災認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務を禁止する規定の創設。現在は、1ヶ月単位の変形労働時間制適用で、最大48日間の連続勤務が可能です。
- 法定休日については、労働者の私生活のリズムを考慮し、予め特定すべきことを法律に規定。
- 副業・兼業については、時間外割増賃金の算定にあたって、本業・副業先双方の労働時間を通算して法定労働時間を超えた場合に割増賃金が発生する仕組みを労働時間管理の負担を考慮し廃止。
ただし、健康管理のための労働時間の通算管理は維持することになります。 - フレックスタイム制において、企業が特定の日や曜日を始業時刻から終業時刻までコアタイムとして設定する「コアデイ」制度を導入。在宅勤務と通常出勤勤務が混在しても在宅勤務時にフレックスタイム制が適用できるようにとの配慮です。
2.どこまで上がる?最低賃金
ここ数年の物価高、国会をはじめとする所得増加の議論などにより、今後も企業に対する賃上げ要請は収まることはないでしょう。気になるのは最低賃金の上昇との関係です。政府は11月に総合経済対策を閣議決定し、賃上・所得の増加を経済成長の柱の1つと位置づけ、2020年代に地域別最低賃金の全国平均1,500円達成を明記しました。ちなみに現在の全国平均は1,054円ですので、あと5年で毎年約90円上がっていく計算となります。
3.在職老齢年金 賃金収入による支給停止の制度見直しの行方は?
企業に勤めながら、月の年金月額と賃金が50万円を超える65歳以上の従業員について、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止にする在職老齢年金制度について、厚労省から50万円の支給停止基準額に見直し案が社会保障審議会に提示されました。高齢者が年金の支給停止を意識し、働き控えをしていることを考慮し就業抑制を防ぐ目的です。
厚労省の見直し案は、(1)在職老齢年金制度自体の廃止 (2)支給停止基準額を71万円に引き上げる案 (3)支給停止基準額を62万円に引き上げる案の3つです。
(2)の「71万円案」は、同一企業における勤続25年以上の労働者が現役期に近い働き方を続けた場合の賃金(61.7万円)に25年以上の加入期間に基づく厚生年金収入(9.7万円)を得ても支給停止にならない水準となります。(3)の「62万円案」は、平均的な収入を得る50歳代の労働者が60歳代で賃金水準の低下が無く働き続けた場合の賃金(52万円)に25年以上の加入期間に基づく厚生年金収入(9.7万円)を得ても支給停止にならない水準となります。
(2)では新たに年間2600万円、(3)では年間1600万円の財源が必要になります。
4.出張における宿泊費の動向は?
当方においても最近特に相談の多い出張宿泊費についてです。物価高に会社の出張旅費規程が追いついておらず、既定の宿泊費では社員の持ち出しが生じるケースが出てきています。ここでは参考として国家公務員の主要な地域での出張宿泊日の上限額を次頁の表で紹介します。
表:国家公務員課長級以下の地域別宿泊費上限額
| 東京・埼玉・京都 | 19,000円 | 北海道・大阪・広島 | 13,000円 |
| 福岡 | 18,000円 | 沖縄・青森・愛知・長崎 | 11,000円 |
| 神奈川・新潟 | 16,000円 | 栃木・群馬・宮城・愛媛 | 10,000円 |
5.障害者雇用率と今後の制度改正見直しは?
民間企業における法定障害者雇用率は、2024年4月から2.5%に引き上げられており、2026年7月には2.7%にさらに引き上げられます。
厚労省は12月3日に障害者雇用制度の在り方に関する研究会を設置し、障害者雇用率制度における障害者の範囲や障害者雇用率未達成の納付金の納付義務対象事業主の範囲を常用労働者100人以下の事業主に拡大すること、障害者手帳を持たない難病患者や精神・発達障害者を雇用率算定対象の障害者に位置付けるかどうかなど、制度見直しについて検討し、2025年度中に方針を取りまとめます。障害者雇用も大企業だけの問題ではなく、今後中小企業も真剣に取組む必要が出てきそうです。
6.フリーランス新法施行による規制の強化は?
11月のフリーランス新法の成立に伴い、労基署では労働者性に疑義のあるフリーランスに対する相談窓口を設け、相談者の申告に基づき委託企業への立ち入り調査を実施します。調査の結果、指揮命令を受けるなど労働者性が認められた場合は、割増賃金未払い、違法な長時間労働、年次有給休暇の付与違反、労災保険不適用などに対し厳しく是正勧告をすることが予想されます。また悪質な事業主に対しては書類送検を躊躇せず行うとのことです。労働者性の判断基準は、当方にお問い合わせください。
7.雇用の流動化は?
危機的な労働力不足のなか、働く側からすれば「会社を辞めても次がすぐ見つかる」、「転職すれば給与が上がる」、「人材サービス会社の活用で自分の市場価値が測りやすい」、「リスキリングの推進」など転職しやすい十分な環境が整っています。厚労省が取りまとめた2021年3月の新規大学卒者の3年後の離職率は、34.9%で、3人に1人は3年で会社を辞めています。しかも採用してから定着させるための国や行政の支援はほとんどありません。当然です。国は転職を推奨していますので。
8.人材確保の動向は?
日本の生産年齢人口は、「2022年版情報通信白書」によれば2050年に5,275万人(対2021年比-29.2%)となる見込みで、ますます労働力不足が進行します。人材確保では、給与が高く、福利厚生が充実し、多様な働き方が実現できる大企業により多くの若年者労働力が集中し、賃上げできない中小企業は事業運営が立ち行かなくなり、そこで失業した人材が大手に流動するといった流れができるでしょう。中小企業が生き残るためには、女性活用はもちろんのこと、高齢者や外国人、育児や介護で通常の就業が困難な者など多様な人材の活用が必須となります。救いは給与や福利厚生だけでなく、仕事のやりがいや自分らしく働けることを求める人が最近増えてきていることです。多様な人材の活用と併せて、仕事や社風、独自性など選ばれる会社となるための施策も重要になります。